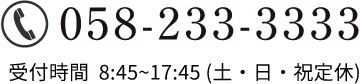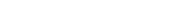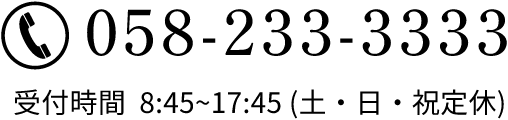令和6年1月1日以降の贈与について
個人向け
2024.11.06 2025.01.11

令和5年度税制改正より、令和6年1月1日以降の贈与について大きな変更がありましたのでお話させていただきます。まずは改正の概要です。
【暦年課税制度】
1.生前贈与加算の期間が3年から7年へと延長された。
生前贈与加算は基礎控除の110万円以下であっても対象となる。
2.1より生前贈与の加算期間が延長したため、相続開始前の4年から7年以内の加算部分については100万円の控除が受けられる。
【相続時精算課税制度】
1.年間110万円の基礎控除額が新設された。
2.1の基礎控除額は非課税のため、生前贈与加算の対象外となる。
3.不動産など一定の贈与財産が災害によって相当の被害を受けた場合、相続の際に被害相当額に対する控除を受けることができる。
では、税制改正後に行う贈与について、暦年課税制度と相続時精算課税制度、どちらを利用したら有利になるでしょうか。
様々な事情により多額な贈与を行いたい方は、どの贈与の方式を選べばよいか迷われる大きな難問です。
結論から申し上げますと、生前贈与の期間が7年以下の場合、「常に相続時精算課税制度が有利」となります。
これは、7年間の控除額が、相続時精算課税制度が770万円であるのに対し、暦年課税では最大100万円にとどまるからです。
また、生前贈与の期間が7年を超える場合でも、財産総額がおおよそ2億円以内であれば「多くの場合、相続時精算課税制度が有利」となります。
これまでの流れから、「相続時精算課税制度を選択したほうが良いのでは」と考えられている方は注意が必要です。
遺贈で財産の取得予定がない推定相続人以外のお孫様等へは、生前贈与加算の適用がなく、贈与税のみで課税関係が完了するため、
相続までの期間に関係なく「暦年課税が有利」となります。
相続税が多額にかかることが見込まれる方は、相続税率(取得する財産に占める相続税の割合)と、
贈与税の実質税率(取得する財産に占める贈与税の割合)とを比較して、贈与を実行すると有効です。
推定相続人でない方への相続時精算課税制度の選択は慎重に検討しましょう。
OTHERS